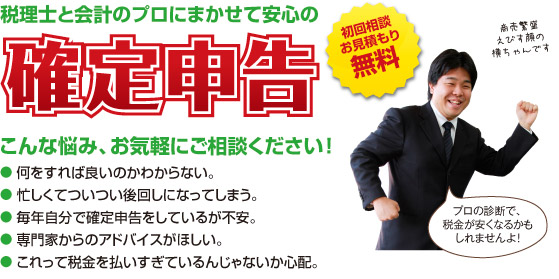

Q1.個人の確定申告とは?
Q2.どんな場合に確定申告をしなければならないか?
Q3.税金が戻ってくる場合は?
Q4.申告手続きの流れについて?
Q5.申告する際、どんな書類が必要か?
個人の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を精算する手続きです。
┃確定申告が必要な方
次のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。
| 1.給与所得がある方 大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要です。 |
|
|||||
| 2.公的年金等に係る 雑所得のみの方 |
次の計算において残額がある。
|
|||||
| 3.退職所得がある方 | 外国企業から受取った退職金など、源泉徴収されないものがある。 ※ 退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は2を参照してください。 |
|||||
| 4.1〜2以外の方 | 次の計算において残額がある。
|
確定申告というと税金を計算して納めるというイメージが強いかもしれませんが、確定申告(還付申告)をすることによって所得税をとり戻すことができるケースがあります。ただし、自ら申告しないと所得税は戻ってきませんので、内容を知らなかったり、忘れている方が周りにいらっしゃったら、是非教えてあげてください。
|
対象者 | 必要書類等 | |
| 医療費控除 | 年間の医療費が10万円を超えた方 | ●給与所得等の源泉徴収票 ●医療費の領収証等 |
|
| 住宅取得等特別 控除 | 住宅ローンを利用してマイホームを取得した方 | ●給与所得等の源泉徴収票 ●住民票 ●土地・家屋の登記簿謄本 ●売買契約書・請負契約書 ●住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書 |
|
| 中途退職者 | 年の中途で会社を退職したあと再就職せず年末調整を受けていない方 | ●給与所得等の源泉徴収票 ●退職後に支払った生保・損保の控除証明書 ●国民健康保険料等の納付書 |
|
| 配当控除 | 配当所得がある方(注)配当控除は住民税には適用されません | ●配当証明書 | |
| 扶養控除 | 出産・婚姻など年末調整後に扶養親族数に異動があった方 | ●扶養親族の氏名・生年月日 | |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領により生活に通 常必要な資産について損失を生じた方 | ●損失の金額を証明する書類 | |
| 寄付金控除 | 国・地方公共団体・特定公益法人等に寄付金を支出した方 | ●寄付金の証明書 | |
| 予定納税 | 予定納税をしている方で確定申告の必要がなくなった方 | ●予定納税の通 知書 |

| 1.必要な書類を準備する | 下記のQ5をご覧ください。 | ||||||||||||
| 2.申告書を準備する | 確定申告書は、「A」と「B」の2
種類から、申告する内容に合わせて選択します。 確定申告書「A」と「B」には、それぞれ第一表と第二表があります。 この手引きは申告書Bを使用する方のためのものです。 次の表で、使用する申告書を確認してください。
次のいずれかに該当する方は、申告書B と分離用又は損失用を併用します。
|
||||||||||||
| 3.付表と計算書等を準備する | 申告内容に応じて、付表と計算書など次のものを準備します。
|
||||||||||||
| 4.申告書を作成する | 申告書を作成します。
|
||||||||||||
| 5.提出する書類を 確認する |
申告書のほか、申告する内容により源泉徴収票などを申告書に添付又は提示する必要があります。 | ||||||||||||
| 6.申告書を提出する | 申告書の受付期間は、 毎年2月16日から 3月15日まで です。 ※ 還付申告の方は2 月15 日以前でも申告書を提出することができます。 |
||||||||||||
| 7.納税する又は 還付を受ける |
納税する方 (1)振替納税を利用する。 (2)窓口で納付する。 (3)e-Tax で納付する。 税金の延納 確定申告により納付する税金の2分の1以上を3月15日までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を5月31日まで延納することができます。 延納を希望される場合には、申告書第一表に必要な事項を記入します。 なお、延納期間中は、利子税がかかります。 還付を受ける方 (1)口座振込で還付を受ける。 (2)郵便局の窓口で還付を受ける。 |
||||||||||||
確定申告に際し、必要になる資料一覧は以下のとおりです。
I:所得控除
| 1.社会保険料控除 | 国民年金・年金基金・健康保険の支払い金額がわかる資料 |
| 2.生命保険料控除 | 一般の生命保険と個人年金保険の控除証明書 |
| 3.地震保険料控除 | 地震保険などの控除証明書 |
| 4.医療費控除 | 医療費の領収証(合計金額が10万円を超える場合) 医療費に対して給付金がある場合には給付金の金額 |
| 5.扶養控除 | 扶養親族の氏名・生年月日・職業 |
| 6.配偶者控除 | 配偶者の氏名・生年月日(所得がある場合には所得金額) |
| 7.障害者控除 | 障害者手帳のコピー等障害者に該当することがわかる資料 |
| 8.寄付金控除 | 寄付、政治献金などの領収証 |
| 9.小規模事業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金払込証明書 |
| 10.住宅取得等特別 控除 | 自己の居住用家屋を新築した人又は増築した人は次の書類 (1) 新築住宅の登記簿謄本 (2) 新築工事の請負契約書・売買契約書・領収証のコピー (3) 建築確認通知書のコピー (4) 住民票 (5) 借入金の年末残高等証明書 |
II:所得金額
| 1.事業所得がある方 | 下記III参照 |
| 2.不動産所得がある方 | 下記IV参照 |
| 3.給与所得がある方 | 給与の源泉徴収票 |
| 4.公的年金等がある方 | 公的年金等の源泉徴収票 |
| 5.配当所得がある方 | 配当に関する受取明細書 |
| 6.保険を解約した方 | 保険会社等から送付されてくる保険の支払調書等 |
| 7.不動産を売却した方 | 下記V参照 |
| 8.株式・ゴルフ会員権を 売却した方 |
(1)売却金額のわかる資料(売買契約書等 (2) 購入金額のわかる資料(売買契約書等) |
| 9.還付金を受取った方 | 還付金の明細書(ハガキ) |
- 現金出納帳・預金出納帳
- 事業に使用している通帳のコピー
- 収入金額の内容がわかる資料
例:売上帳、請求書、領収証
- 必要経費
租税公課 固定資産税の納付書、事業税の納付書、自動車税の納付書など 保 険 料 火災保険、地震保険、自動車保険料など事業に係るもの 修 繕 費 事業に係る修繕の請求書と領収証 減価償却費 新規に取得した資産の請求書と領収証
廃棄及び売却した資産と売却金額借入金利子 借入金の返済予定表 地代家賃 事業に係る家賃・地代などの契約書のコピーと支払金額 給料賃金 支払った給料の金額の明細 外 注 費 請求書・領収証 そ の 他 水道光熱費、通信費・広告費などの領収証
- 収入金額
賃貸料収入(地代収入)の明細
礼金収入の明細
更新料収入の明細
預り敷金の明細
新規契約者の賃貸借契約書のコピー
- 必要経費
租税公課 ―固定資産税の納付書、事業税の納付書 保 険 料 ―火災保険、地震保険など賃貸物件に係るもの 修 繕 費 ―賃貸物件の修繕の請求書(又は見積書)と領収証 減価償却費 ―新規に取得した資産の請求書(又は見積書)と領収証 廃棄及び売却した資産と売却金額 借入金利子 ―借入金の返済予定表 地代家賃 ―賃貸物件の家賃・地代などの契約書のコピーと支払金額 給料賃金 ―支払った給料の金額の明細 外 注 費 ―請求書・領収証 そ の 他 ―賃貸に係るその他の経費の領収証
支払調書を受取った場合には、その支払調
- 収入金額
収入金額の入金が確認できるもの(入金日・入金額・入金場所)
- 取得費 譲渡資産の取得価額がわかる資料
例:購入したときの売買契約書
不動産取得税納税通知書
仲介手数料領収証
- 必要経費
仲介手数料 −仲介業者の領収証、振込控え 登記関連費用 −領収証等 立退料 −振込控え 印紙代 −領収証 建物取壊費用 −見積書、請求書、領収証 その他 −資産を譲渡するのに特別に要した費用
- その他
売買契約書
登記簿謄本(持分・取得日等の確認)
住民票(居住用財産を譲渡した場合)
各種証明書(収用等の場合)
相続税申告書(納税猶予の適用を受けている場合)
消費税申告書(事業用資産の場合)
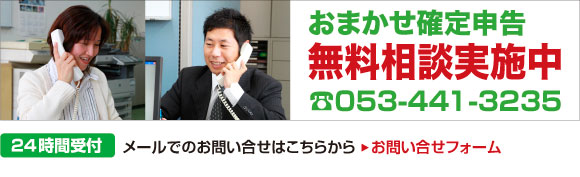
| 株式会社 松本会計センター 〒432-8053静岡県浜松市中区法枝町89-3 TEL(053)441-3235 FAX(053)441-3314 |
▲ページのトップへ |